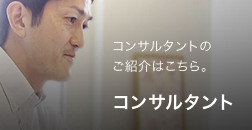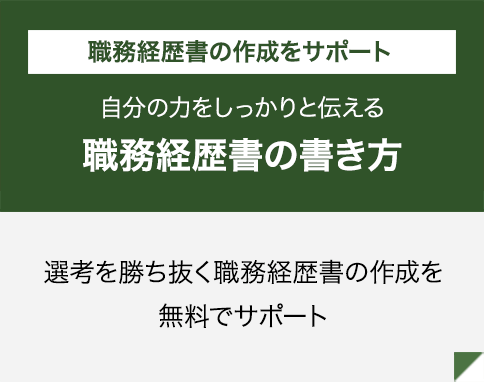CxO(最高○○責任者)へのキャリアを目指す人が増えている
かつてはほぼ外資系企業にしか見られなかったCEO(最高経営責任者)、CFO(最高財務責任者)、COO(最高執行責任者)といった“CxO”という肩書。今では日系企業にも一般的なものになってきており、ニュースなどでよく耳にする上述のもの以外にもCMO(最高マーケティング責任者)、CTO(最高技術責任者)、中にはCHO(Chief Happiness Officer/最高社員幸福責任者)といったポジションまで登場しています。その流れと並行して、投資銀行やコンサルティングファームでの業務経験を持つプロフェッショナル人材が、CxOポジションで事業会社に転職するケースが年々増えています。特にVCなどからの資金調達が比較的容易になりスタートアップが盛り上がりを見せている近年は、大きくなっていく組織を取りまとめて、会社としてのステージを一つ上へと引き上げられるようなリーダーが求められる傾向が強まっています。
ここではCxOとして転職することを考えているユーザーに向けて、採用マーケットの展望や転職のメリット、リスクなど、考慮しておくべきポイントについて解説いたします。
CxOポジションの求人が増えている理由とは
CxOを求める求人が増えているのには、どんな背景があるのでしょうか。考えられる主な理由についてまとめてみました。
●理由その1「スタートアップ、アーリーステージ企業における経営層の新設、強化」
調査会社ジャパンベンチャーリサーチによるとスタートアップ企業の資金調達額は年々増加しており、2012年に650億円だった調達総額は2017年には2921億円、2018年はさらに増えて4000億円近い水準で着地するとされています。その背景として、既存のベンチャーキャピタルだけでなく、トヨタ自動車やKDDIなど大手事業会社が資金の出し手として多額の投資を直接行うようになっていることがあります。一方、スタートアップ側は流入する投資マネーの一部を採用に振り向け、優秀な人材をマネジメントとして迎えようと動いています。そのため、営業やマーケティング活動の統括、組織人事面の刷新、最適なITシステム構築といった、さまざまな業務をリードするCxOポジションの求人が増えています。
●理由その2「新規事業や新拠点の立ち上げにともなうリーダー枠の募集」
現代の企業には、その大小にかかわらずデジタル化、グローバル化の波が押し寄せています。この変化の速い時代には、これまでのように事業に必要な人材が社内から育つのを待つといった悠長なスタンスではいられません。新規事業を立ち上げる、あるいはこれまで商圏ではなかった地域に拠点を新設する、といった、企業にとって重大な取り組みをスピーディに展開するためには、すでにその能力を有している外部人材を登用し、即戦力リーダーとしてプロジェクトを牽引してもらう必要が出てくるのです。社会全体の転職に対する寛容度が増加し、ある程度キャリアを積んだシニア層が転職しやすい環境になってきたのも、ひとつの要因と考えられます。
●理由その3「M&Aや事業承継による経営層の交代」
大企業の非主流事業のカーブアウト、あるいは後継者難に見舞われた中小企業の事業承継など、日本においてもM&Aはごく当たり前に行われるようになりました。投資ファンドなどへの株主の大幅な変更は、時に経営陣の刷新につながることがあります。その場合に、過去のしがらみに縛られることなく大ナタをふるえるような、経営プロフェッショナルのスキルが求められるケースがしばしば見られます。この場合も、具体的なCxOポジションとして人材マーケットに求人が出てくることになります。
CxOとして転職することのメリット
プロフェッショナル人材がCxOとして事業会社に転職する際には、どのようなメリットが期待できるでしょうか。いくつかのポイントを見ていきたいと思います。
●メリットその1「自らビジネスをドライブさせることが出来る」
CxOポジションに限った話ではありませんが、プロフェッショナルファームから事業会社に転職することを決めた方の多くが、その理由として「アドバイザーとしての立場ではなく、自分が当事者として経営に携わりたかった」とおっしゃいます。投資銀行でM&Aディールを実行した後、あるいはコンサルティングファームで経営戦略を策定した後、クライアント企業が期待した通りに成長するかどうかは、アドバイザーの立場ではコミットすることが出来ません。そこに物足りなさを感じ、自らが会社を動かしていきたいと考えるこういった志向の方は、CxOの立場での転職にふさわしいでしょう。
●メリットその2「将来的に大きな収入を得るチャンスがある」
現在のCxOの年収相場は、ベンチャー企業では平均すれば800万円前後、多少良くても1000万円台前半が上限と考えられます。高給で知られる投資銀行やコンサルティングファームで働いている方であれば、ほぼ100%の確率で給料は下がるでしょう。ただし、ベンチャーには魅力的な制度があります。それがIPOを前提としたストックオプション制度です。入社時に一定のストックオプションを付与されたCxOが会社を大きく成長させ、株式の上場を迎えて多額の売却益を手にする、というのは非常に夢のあるサクセスストーリーです。その実現性を確信できれば、足元の年収はあまり問題にならないかもしれません。
●メリットその3「プロ経営者へのキャリアマップが描ける」
管理職と経営陣は連続したキャリアのように見えて、実はまったく異なる職務です。経営陣は会社独自のビジョンを掲げてそれに沿った戦略を策定し、経営資源を獲得してくることが仕事です。一方、管理職はその戦略をメンバーを取りまとめて滞りなく実行することが求められます。なるべく早い段階で経営サイドに立って実績を積み重ねていき、自分の市場価値を継続して高めることができれば、将来的にはプロの経営者となっていくキャリアマップが想定できます。
CxOとして転職する際のリスク
他のあらゆる転職と同じように、CxOとしての転職にもリスクはあります。以下に想定されるリスクについて挙げてみます。
●リスクその1「早期に成果を出すことへのプレッシャーが強い」
即戦力として採用するからには、出来るだけ早く成果を出してほしいというのが採用側企業の偽らざる意識です。そのプレッシャーは有形無形のさまざまな姿となって、CxOであるあなたの前に立ちはだかります。CxOとして入社したものの、期待値を超えることが出来ず半年も経たずに退職してしまう、というケースも実際に見られます。入社後に求められている職務内容と、それを遂行する実力が自分にあるのかを、事前に冷静に分析することを忘れるべきではありません。
●リスクその2「会社自体の基盤がぜい弱な場合がある」
大手や老舗企業には、ある程度確立されたヒト・モノ・カネがあり、市況が不安定になってもしばらく耐えうるだけの基盤があります。ところが、CxOを外部から求める企業においてはそうした資源に乏しい場合が多く、市況の影響をもろに受けてしまい、最悪の場合は倒産してしまう可能性があります。外部環境の変化があったと仮定した時に転職先企業がどんな将来を迎えるのか、よく見据える必要があります。
●リスクその3「転職先の企業にいつまでも馴染めない」
前職でしっかりと実績を出してきたからこそCxOとして期待されて採用された、ならばその経験を生かしてどんどん改革を進めていこう。こう考えてしまうのも理解できます。ですが、どんなに小さな会社にもそれぞれの仕事のやり方、ルール、人間関係があります。それを謙虚に理解しようとせず、CxOという権威をかさに着て振舞うようなスタンスでは、既存メンバーがついてくることは期待できません。前職のやり方を持ち込むことにこだわりすぎず、周囲と密なコミュニケーションをとって新しい環境を受け入れる柔軟性が重要になります。
もうひとつ、転職先がオーナー企業である場合は、そのオーナーとの相性も非常に重要なファクターになってきます。成長性の見込める分野で魅力的なプロダクトも有している、と判断してCxOとして入社したものの、一緒に働いてみて初めてオーナーとの相性が良くないことに気づき早期退職を余儀なくされるというケースは少なくありません。こうした部分は面接の場ではお互いなかなか見えにくいものですので、第三者であるエージェントなどに意見を求めてみるのも有効かと思われます。
最後に
変化が激しい経営の現場において、経験・ノウハウと、自らも手を動かせる行動力を兼ね備えた優れた人材がCxOとして求められる流れは、今後も続くものと思われます。
自らが目指すキャリアのゴールが明確で、その延長線上にCxOとして働くという選択肢がある方は、ぜひ一度、CxOポジションの求人を豊富に取扱っている弊社アンテロープのような転職エージェントに話を聞きにいらしてください。最新のマーケット状況や過去の事例など、エージェントが持っている情報は事前のリサーチに大きく役立つでしょう。
なお、弊社が取り扱っている最新のCxO関連求人はこちらからご確認いただけます。ぜひチェックしてみてください。
「CxO/事業統括関連の求人」
監修:アンテロープキャリアコンサルティング
この記事は、アンテロープキャリアコンサルティング株式会社が監修しています。ハイクラス人材の転職に役立つ情報を発信しています。 |