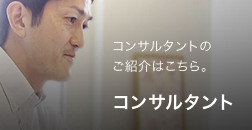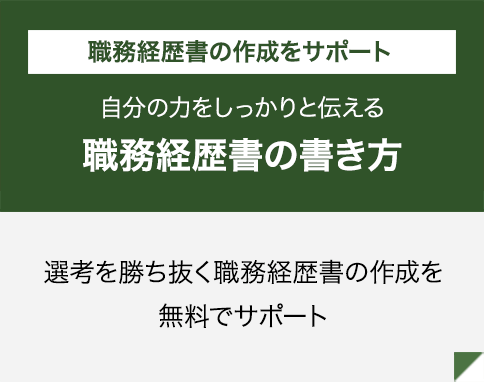ここでは、PEファンドのビジネスモデルや日本での歴史、仕事内容などをご紹介します。併せて、PEファンドに転職する際に求められる経験やスキル、英語力についても見ていきましょう。
<目次>
PEファンドの基本情報
PEファンドの仕事紹介
PEファンドへの転職で求められる人物像
PEファンドで必要とされる英語力
PEファンドへの転職
PEファンドの基本情報
プライベートエクイティ投資とは、成長余地はあるものの何らかの要因でその潜在的な成長力を活かしきれていない企業に投資をし、企業価値を高めてからExit(IPO、他社への売却等)してファイナンシャルリターン獲得を目指すビジネスをいいます。3~5年程度で手放すことを前提に買収を行い、その手法によりMBO(Management Buyout)、LBO(Leveraged Buyout)等と区分けされます。また、投資する資金の出元により、ファンド(私募で集めた機関投資家等の資金+自己資金+ローン)、プリンシパル(自己資金+ローン)等と分類したりもします。
投資対象となる企業は、主に「大企業の子会社/非主流部門」や「オーナー系中堅企業」であり、それらの企業の株式を引き受けるという形で投資を実行します。最近はいわゆる「再生案件」は比較的少数派ですが「事業再生」「ディストレス」「不良債権」投資も一部この業界に含まれます。
日本で最初に投資ファンドが世間で注目されるようになったのは、1998年の米・リップルウッドによる日本長期信用銀行の買収の頃からです。当時は「ハゲタカ」と揶揄され、非難される傾向がありました。現在でもマスコミ等の影響もあって、一部ネガティブなイメージを持たれるケースもありますが、ファンド側もそれを意識し、徹底して「日本的な」振る舞い(礼儀、マナーやビジネス慣習など)をもって対外的な活動を行うようになっています。現在では、外資系ファンドよりも純粋な日系ファンドが多くなってきており、特に中堅企業の買収などでは日系ファンドの活躍が目立ってきています。
ファンド規模は数十億円から大きいもので数千億円を超えるものも出てきていますが、社員数でいうと外資系・日系とも各社10~20人程度のプロフェッショナルが在籍していて(大きいところでは例外的に50人程度抱えているファンドもあります)、少数精鋭でこれらを回しているという形です。
主なプレーヤーとしては、外資系ではカーライル、KKR、ブラックストーン、ベイン・キャピタル、ペルミラなどが有名で、国内は独立系のアドバンテッジ・パートナーズ、ユニゾン・キャピタル、エンデバー・ユナイテッド、インテグラル、日本産業パートナーズなどの他、金融機関系のジャパン・インダストリアル・ソリューションズ(JIS)、野村キャピタル・パートナーズ、大和PIパートナーズ、さらに商社系の丸の内キャピタル、三井物産企業投資、アイ・シグマ・キャピタルなども存在感を示しています。これ以外にも投資銀行などが、ファンドやプリンシパルでのバイアウト投資を行っているものもあります。
プライベートエクイティ/投資ファンドの主要企業リスト
PEファンドの仕事紹介
PEファンドの仕事は、大きく「投資前」「投資後」に分けることができます。「投資前」は更に「投資案件のソーシング(案件探し・検討・交渉)」「投資のアレンジ、実行」に分かれ、「投資後」は「経営戦略の策定・実行支援(バリューアップ)」「モニタリング」「M&A支援」「Exit」等に分けることができます。以下、それぞれの仕事内容について説明いたします。
<投資案件のソーシング(案件探し・検討・交渉)>
ファンドの投資方針に沿い、かつ予め設定した投資対象に合致した案件を探し出します。投資方針は、どのくらいの株式を保有するのか、経営関与へのスタンスをどう取るのか等、ファンドによってかなり異なります。当然、投資対象に関しても企業規模(売上高、EBITDA等の指標で設定することが多い)、業界・業種、地域ほか様々な基準をファンド毎に決めています。実際のソーシングは、投資銀行、証券会社、銀行といった金融機関や事業会社からの紹介等によることもあれば、公開情報から潜在的な成長余力を見極め、自ら投資提案を持ち込むこともあります。実際に投資の実行に至るまでには、年単位の長い期間がかかることもあり、高い提案力が求められます。
<投資のアレンジ、実行>
投資スキームの検討、ファイナンスのアレンジ、資本政策(経営陣/従業員へのインセンティブプランの立案・実行を含む)、エグゼキューションを行います。全てを自分達で行うわけではなく、外部の証券会社や法律事務所などを使ったりすることもあります。例えば、投資対象となる企業のデューデリジェンスに関しては外部のFAS(Financial Advisory Service)に依頼する、といったイメージです。
<経営戦略の策定・実行支援(バリューアップ)>
具体的には、短中期の経営計画の策定、業務オペレーションの改善(例:工場の生産性の向上)、財務再構築(資金調達の効率化、借入金のリファイナンス等)、成長戦略支援(社内組織の活性化、商品・サービスの開発強化、新規事業立ち上げ、取引先開拓、人材採用等)を行います。この部分に力を入れているファンドを「ハンズオン志向が強い」と表現します。
<モニタリング>
企業パフォーマンスのモニター 、日々の営業活動・資金の動きなどを分析、財務及びオペレーションの結果分析、予算プロセス及び監査プロセスへの関与等を行います。
<M&A支援>
投資先企業自体のM&A支援です。例えば、価値向上に寄与するアドオン企業の買収、垂直統合、不採算部門の売却、資本提携等を行うことがあります。
<Exit>
投資した企業を他社へ売却したり、株式公開することを通じて投資資金を回収します。簡単にいうと100億円投資をして300億円で売却、投資家に元本分と当初に約束をしたリターンを支払い、残った部分が投資ファンドの取り分となります。元本を超えた部分の、例えば20%程度とすれば、200億円×20%で40億円がファンドの利益となります。
PEファンドへの転職で求められる人物像
PEファンドのフロント業務は主に、ソーシング(案件探し)、バリュエーション(価値評価)、エクセキューション(投資実行)、バリューアップ(成長、再生)、Exit(売却、IPO)となり、これらの業務、特にソーシングからバリューアップまでの実務経験がある即戦力人材がベストです。具体的には、ファイナンスのバックグラウンドやプロジェクト遂行力・経営改善力を持った人材が求められます。ファンドによっては、投資前・投資後で部署やチームを分けているところもありますが、ほとんどのファンドは若手でも投資前から投資後まで一気通貫で全ての業務に関わります。従って、エクセキューションだけできる、ファイナンスには弱いが事業運営だけは得意、というスキルセットでは評価は比較的低くなってしまい、万遍なくすべてに精通することが重要になってきます。もちろん、若手人材で最初からそれらを全部身につけている方はなかなかいませんから、入口としてはM&Aアドバイザリー経験者、戦略コンサルファーム出身者などが入社していくことが多いです。なぜM&A経験が重視されるかというと、投資前である買収と売却の局面でPE内部で行われることは、まさにM&Aそのものだからです。一方、なぜ戦略コンサルファームでの経験が重視されるかというと、投資後に投資先の経営を見る力が必要になってくるからです。そして、入社後はどちらの出身者も、投資前から投資後まで全てをカバー出来る人材になることが求められます。
求められる資質を一言でいうと、高い対人コミュニケーション力、リーダーシップです。外資系ファンドでも日系ファンドでも、投資先は主に日本の企業になりますし、地方の中堅・中小企業などへ投資を行うこともよくあります。その時、オーナー型の経営者などとも腹を割って話し、信頼を得られるような人間性がなければ、まず交渉のテーブルに着くことすら難しくなってしまいます。また、ファンドの仕事は実際には様々なステークホルダーを巻き込んで推進していきます。外部の投資銀行、FAS、コンサルティング会社、法律事務所など、さまざまなプロフェッショナルたちと協働しながら、タイトなスケジュールでのプロジェクトを推進していくことになります。その意味でもプロジェクトマネージメント力、リーダーシップといった素養が求められます。言い方を換えると、時には冷静な分析力や判断力を持ちながら、投資家や投資先の気持ちを理解できる熱い心も持ち合わせている必要があるのです。
PEファンドで必要とされる英語力
PEファンドにおいて、英語力が求められる場面は多くあります。外資系であっても日系であっても投資先自体は国内企業であることが大半ですが、近年はその投資先企業が海外展開をしていくようなフェーズにいる場合も多いですし、外資系PEであれば投資の意思決定プロセス等で海外オフィスとのコミュニケーションなども当然発生します。
この業界は、海外MBAホルダー等の社員もたくさんいるので結果として高いレベルのビジネス英語力を持つ方が多いのは事実ですが、一方で、特に日系ファンドであれば、海外未経験でも入社時点としては一般的なビジネスレベルの英語力があれば問題ないのが普通です。とはいえ、IRなど投資家から資金集めをするフェーズに業務で関わる場合は別で、ここでは外資系日系にかかわらず海外投資家から直接資金を集めることが多いため、外国人と交渉ができるレベルが求められます。この場合は実質、帰国子女クラスの英語力を持った方が求められることが多いです(IR専属でポジションを置いているファンドも多くあります)。
実際の選考ですが、日系ファンドでは経歴やTOEICの点数等から英語スキルは判断材料の一つにはなりますが、英語面接になることはまずありません。外資系ファンドの選考はケースバイケースで、ジュニア採用の場合は日本人面接のみで判断されることもありますし、中堅クラス以上の社員を採用する場合は最終的に本国との英語インタビューを課すところもあります。
PEファンドへの転職
PEファンドへの転職をお考えなら、アンテロープにお任せください。あなた専任の当社エージェントが、過去の実績に基づいた応募書類添削・面接対策などのサービスを無料でご提供し、難関であるファンド業界への転職活動を強力にサポートいたします。
監修:アンテロープキャリアコンサルティング
この記事は、アンテロープキャリアコンサルティング株式会社が監修しています。 コンサル業界・金融業界への転職に役立つ情報を発信しています。 |